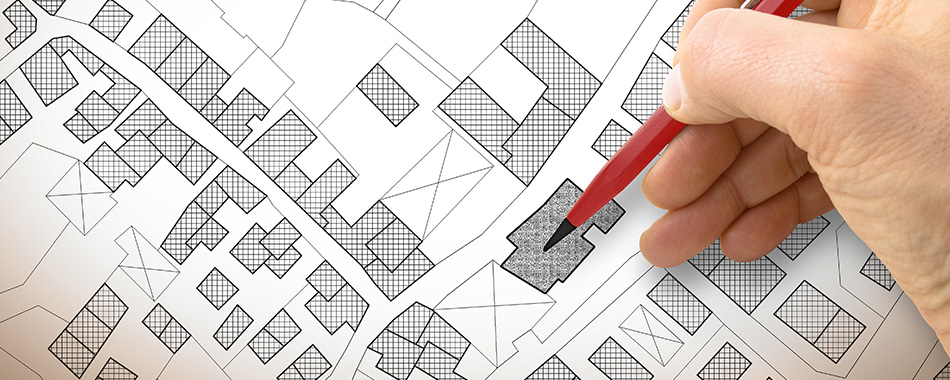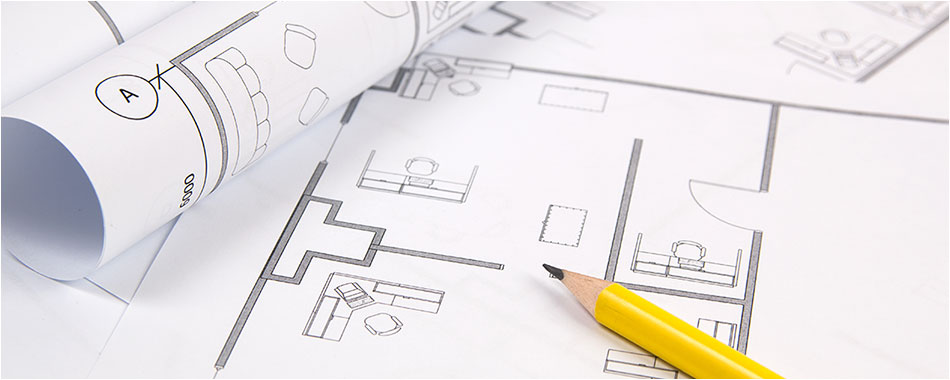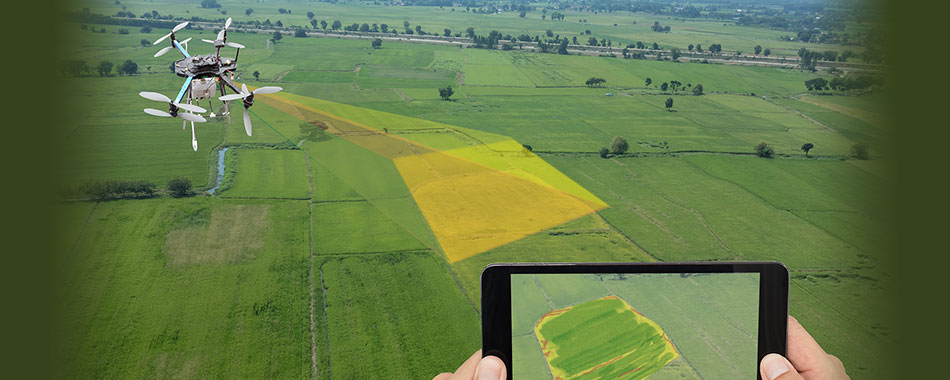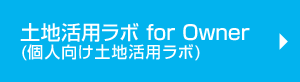コラム No.53-43
コラム No.53-43PREコラム
戦略的な地域活性化の取り組み(43)公民連攜による國(guó)土強(qiáng)靭化の取り組み【5】東京一極集中の是正
公開(kāi)日:2022/01/11
「國(guó)土強(qiáng)靱化年次計(jì)畫2021」(內(nèi)閣府)では、2020年に引き続き、(1)激甚化する風(fēng)水害や切迫する大規(guī)模地震等への対策、(2)予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策、(3)國(guó)土強(qiáng)靱化に関する施策を効率的に進(jìn)めるためのデジタル化等の推進(jìn)を緊急対策としていますが、人口の東京一極集中を是正することも、重要な課題となっています。
國(guó)土交通省の「東京一極集中の是正方策について」
國(guó)土交通省は、2020年11月に「東京一極集中の是正方策について」を公表し、東京圏では広範(fàn)囲で地震によるリスクが想定されるほか、水害による広域での浸水被害などの可能性があり、諸機(jī)能?施設(shè)が東京に集中することに対する是正の必要性を提唱しています。
しかし実態(tài)としては、居住地を選択する際に半數(shù)が地震災(zāi)害のリスクを考慮しておらず、地震災(zāi)害リスクへの認(rèn)識(shí)が十分でない可能性があること、逆に、東京圏からの圏外への転出者は、居住地選択において地震災(zāi)害リスクを考慮している割合が高いことを指摘しています。
また、ほぼ完全にテレワークでの勤務(wù)が可能となった場(chǎng)合でも、子どもと同居している世帯では、「子育て?教育上の都合」という理由で「引っ越しを検討したい」とする割合は低くなっています。(國(guó)土交通省「東京一極集中の是正方策について」より)
東京一極集中の狀況
最新の東京都の公表資料によると、2020年から2021年前半にかけて、特に區(qū)部において人口流出による人口減少が見(jiàn)られますが、一方でその減少率は縮小傾向にあり、東京都の人口減少が中長(zhǎng)期的に継続するとは、考えにくい狀況です。
內(nèi)閣府「國(guó)土強(qiáng)靱化年次計(jì)畫2021」の資料によると、東京圏(東京都?神奈川県?埼玉県?千葉県)では、転入超過(guò)數(shù)は減少しているものの、依然として流入超過(guò)となっています。東京圏においては、2011年の東日本大震災(zāi)時(shí)にも転入超過(guò)數(shù)が一時(shí)的に大幅減少し、その後増加に転じており、大規(guī)模なインシデントが発生した際の、東京を中心とした大都市圏における人口動(dòng)態(tài)の特徴ともみてとれます。
とはいえ、東京一極集中の是正は、大規(guī)模災(zāi)害に対応するBCPの観點(diǎn)からも必要なことに変わりはありません。國(guó)も、2018年2月に東京23區(qū)の大學(xué)の定員増加を2028年3月末までの10年間抑制する法案を閣議決定するなど、東京一極集中要因への対応を進(jìn)めていますが、高度に都市機(jī)能が発達(dá)した大都市の人口を分散させることは、簡(jiǎn)単ではなさそうです。
テレワークが人口の偏在を解消するものではない
2020年、新型コロナウイルス感染癥の拡大に伴って緊急事態(tài)宣言が発出され、各企業(yè)に対して在宅勤務(wù)が要請(qǐng)されたことから、テレワークという働き方が浸透しました。一部の企業(yè)は、東京都內(nèi)にある事務(wù)所を閉鎖、縮小したり、本社機(jī)能を地方に移転したりするなどの動(dòng)きがあったことから、このような動(dòng)向が続くことで、東京一極集中が是正されていくのではないかとの見(jiàn)方がありました。確かに、企業(yè)における日常業(yè)務(wù)の中には、テレワークで十分機(jī)能する場(chǎng)合があり、働き方改革に有効な手段ではあります。一方で、経営企畫や新規(guī)事業(yè)開(kāi)発、顧客開(kāi)拓など、やはり対面によるコミュニケーションが不可欠であることを認(rèn)識(shí)した方々も多かったのではないでしょうか。また、教育現(xiàn)場(chǎng)におけるリモート學(xué)習(xí)が學(xué)生に與えた影響などを考えても、人同士が集會(huì)することの重要性を再認(rèn)識(shí)させられたと思います。結(jié)局のところ、テレワークは、コロナ禍のような非常時(shí)に人と人との接觸を抑制する手段としては大変有効であり、多くの國(guó)民がその有用性を経験したことの意義は大きいと思いますが、あくまでコミュニケーションの補(bǔ)助機(jī)能であり、それ自體がNew Normal(新しい生活様式)を誘発し、東京一極集中を是正するものではなかったようです。
やはり、企業(yè)や公的機(jī)関、學(xué)校にとって、交通、物流、情報(bào)基盤が集中し、高度に発達(dá)した東京という都市機(jī)能が本當(dāng)に必要なのか、社員や職員、學(xué)生を生活コストが高い東京に流入させることが、それぞれ組織の生産性向上につながっているのかを考えることが重要なことではないでしょうか。
前出の、國(guó)土交通省「東京一極集中の是正方策について」でも、「東京一極集中是正に係る既存の取り組み例」として、以下の例を紹介しています。
- (1)地方創(chuàng)生推進(jìn)交付金(移住?起業(yè)?就業(yè)タイプ):東京から地方に移住して起業(yè)?就業(yè)する方々へ支援金を支給する取り組みを行う地方公共団體を支援。
- (2)地方拠點(diǎn)強(qiáng)化稅制:企業(yè)が本社機(jī)能の地方移転又は地方拠點(diǎn)の強(qiáng)化を行う場(chǎng)合の稅制優(yōu)遇措置として、オフィス減稅(建物等の取得価額に対する特別償卻又は稅額控除)及び雇用促進(jìn)稅制(常時(shí)雇用従業(yè)員の増加數(shù)に応じた稅額控除)を適用。
- (3)地方大學(xué)?産業(yè)創(chuàng)生法:産官學(xué)連攜により、地域の中核的産業(yè)の振興や専門人材育成などを行う優(yōu)れた取り組みを「地方大學(xué)?地域産業(yè)創(chuàng)生交付金」において重點(diǎn)的に支援し、「キラリと光る地方大學(xué)づくり」を進(jìn)め、地域における若者の修學(xué)?就業(yè)を促進(jìn)。特定地域內(nèi)(東京23區(qū)內(nèi))の大學(xué)の學(xué)部等の定員増を原則10年間抑制。(國(guó)土交通省「東京一極集中の是正方策について」より)
全國(guó)には、地域の中核となる福岡、広島、大阪、名古屋、仙臺(tái)、札幌といった主要都市があります。これら都市インフラが整備された地方都市に、まずは國(guó)の行政機(jī)関や公的組織を機(jī)能移転あるいは移譲させ、さらに地域の中核都市を、「モノづくり都市」、「學(xué)園都市」、「情報(bào)都市」、「金融都市」、「田園都市」など、行政機(jī)能と関連づけて多極集中するといった、戦略的で機(jī)能的な國(guó)土開(kāi)発を公民連攜によりデザインしていくことも検討していく必要があるかもしれません。