メニュー
Sustainable Journeyは、
2024年3月にリニューアルしました。

連載:みんなの未來マップ
2025.9.29
江守さんのロングインタビューはこちら
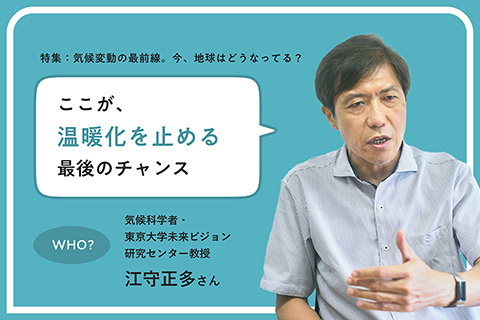
氷河期は今から「たった6℃」低いだけ。溫暖化を止めるためにできることを、本気で考えよう
詳細を見る以前から地球溫暖化や気候変動について研究し、予測データを基に警鐘を鳴らし続けてきた地球溫暖化?予測研究の第一人者、気候科學者の江守正多さん。地球溫暖化は問題の壯大さゆえに、一人ひとりが自分事として捉えづらい傾向があり、なかなか事態は好転していません。
なぜ、地球溫暖化を止めなければならないのか。人権の観點から考えるとともに、江守さんが、いつか見屆けたい未來について伺いました。
江守さんは以前、私たちが今、溫暖化を止めないのは、將來世代の虐待にも等しいことだと仰っていました。
地球溫暖化を引き起こしたのは、これまでの文明を築き上げてきた私たちです。にも関わらず、過酷な環境下での生活を余儀なくされることになる溫暖化を止めようとしないのは、「將來世代に対する人権侵害」にあたるのではないでしょうか。ですから「後から生まれてくる人はかわいそう」で済ませてはいけないということが、新たな常識にならないといけないと思っています。

つまり、人権という観點からも気候変動を捉える必要がある。
そうですね。ただ、人権侵害の対象が將來世代である地球溫暖化問題の場合、その意識が芽生えるのはすごく難しいと思っていました。実は人類の歴史では、見落とされていた人権が回復していくということが何度も起きています。例えば、ある時期までは當たり前だった奴隷や植民地が良くないことだとされて、奴隷だった人たちにも人権を認めるべきだと世界の常識が変わっていきました。女性の參政権などもそうですね。いずれにしても、人権侵害されていた當事者たちが立ち上がって聲を上げ、それまでの常識を変えていった歴史があるんです。
でも將來世代は、生まれていたとしてもまだ子どもだし、これから生まれてくる人は當然、聲を上げられない。でもとうとう、2018年にグレタ?トゥーンベリさんが出てきて、大人に対してすごく怒った。「いよいよ將來世代の反亂が起きた!」と思いました。

?teamtime
その後、世界の各地で子どもたちが連帯して大規模なデモを行いました。中でもドイツでは約140萬人が參加し、社會に大きな影響を及ぼしました。グレタさんにしろ、デモにしろ、起こるべくして起きたことではないでしょうか。

?DisobeyArt
今の常識だけでは、どうしても將來世代の人権を考えることは難しい。例えば奴隷が當たり前にいた時代、その文化圏において、子どもが「お父さん、奴隷はかわいそうじゃないの?」と素樸に聞いたとします。お父さんは「かわいそうかもしれないけど、奴隷がいないと経済が回らないからしょうがない」と言うかもしれません。溫暖化も同じです。「今、CO2をたくさん排出しているせいで將來は大変なことになるらしい。でも、そんなこと言っても経済が回らないんだからしょうがない」と多くの人は思っているわけです。
確かに、そうした意識は多かれ少なかれあるかもしれません。
だけど、もし世界が脫炭素化に成功した暁には、その時代の人たちから私たちは「當時の人たちはひどいことをしたね」「將來世代に迷惑をかけてよく平気だったね」と言われると思います。こうした未來の常識を想像していかないと、人権という視點は獲得することができないんです。
最近は、「持続可能性が大切だ」とみんなが言うようになりました。しかし、何をいつまで持続させるかは誰も具體的に語っていないし、なんとなく言っているだけのような気がします。私は、それだと心許ないと思うんですね。だから思考実験として「持続しない」選択肢があることを意識するのがいいのではないかと考えています。
「持続しない」選択肢?
以前出した本で「文明のターミナルケア」ということを書きました。環境も破壊されたし、資源もなくなってきたから、今回の文明はこれで終わろうと世界で合意し、子孫はつくらずに資源を使い盡くし、お祭りをやりながら滅びていく。そういう選択肢は、理論的にはあり得ますよね。このように「持続しない」という選択肢があることを意識すると「持続する」ことが選択肢として浮かび上がり「それを積極的に選び取っている」という感覚になります。
確かに。
自分でどうしたいかを選び取って初めて、どんな未來を望むのかが考えられるようになるのではないかなと思います。
私は2050年で、ちょうど80歳になります。その時に、世界のCO2排出量が実質ゼロになっていてほしい。現狀のぺースではゼロにするのは難しそうなんですけれども、それでもある程度、気候変動問題が解決に向かっていることは見屆けたいですね。「人類は気候変動問題を克服したなぁ」と思いながら死にたいです。

せめて、安心して見屆けたいと。
気候変動を克服するというのは、単に技術やシステムが入れ替わるだけの話ではありません。國際協調もしなければいけないし、保守とリベラルの対立も乗り越えなければなりません。そういうことも含めて、気候変動という問題を人類が乗りきったと言えるのが、私が見てみたい未來です。

1970年神奈川県生まれ。東京大學教養學部卒業。同大學院総合文化研究科博士課程修了。博士(學術)。1997年より、國立環境研究所に勤務。同研究所気候変動リスク評価研究室長、地球システム領域副領域長などを経て、2022年より東京大學未來ビジョン研究センター教授。専門は気候科學。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次および第6次評価報告書の主執筆者。著書に『異常気象と人類の選択』(角川SSC新書)、『地球溫暖化の予測は「正しい」か?』(化學同人)、共著書に『地球溫暖化はどれくらい『怖い』か?』(技術評論社)などがある。
大和ハウスグループも「生きる歓びを、分かち合える世界」の実現に向け、様々な取り組みを進めていきます。

Sustainable Journeyは、
2024年3月にリニューアルしました。