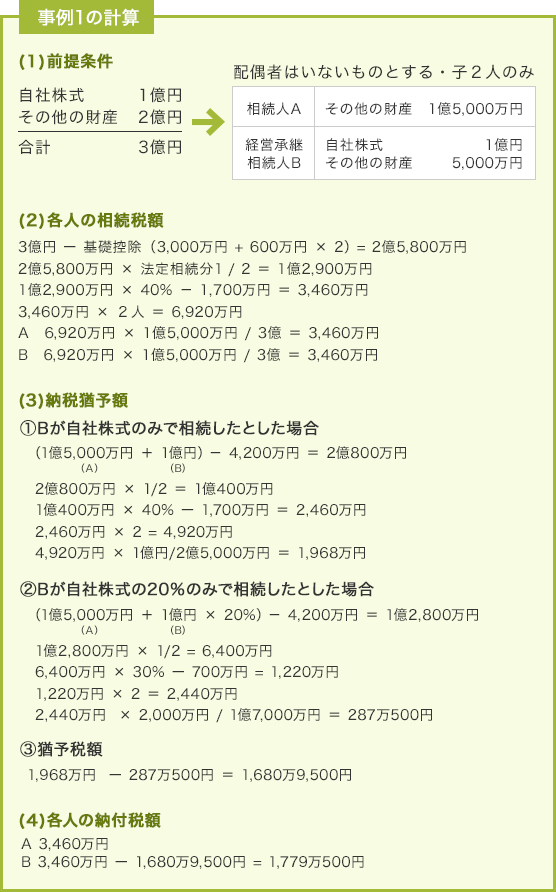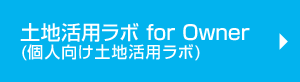コラム No.39-4
コラム No.39-4トレンド
今仲清の事業承継シリーズ(4)2018年度稅制改正で事業承継の條件緩和を計畫
公開日:2018/01/31
日本の産業を支えている中小企業の事業承継をスムーズに行うために、政府?與黨は2018年度稅制改正で、承継する非上場株式のすべて(現在は3分の2)について贈與稅?相続稅を猶予し事業を継続する限り贈與稅?相続稅の納稅を猶予するなど、事業承継の條件を緩和する計畫です。それまでは現行の事業承継支援策、たとえば自社株式等の相続稅の納稅猶予制度などを活用することで、有利な事業承継が可能になります。
2018年度稅制改正のポイント
「中小企業の承継、相続稅を猶予政府?與黨が廃業対策」と、『日本経済新聞』(2017年11月22日)で政府?與黨が2018年度稅制改正で、中小企業の世代交代を促すための稅優遇を拡大すると報じられました。その背景には、現行の制度では全株式の3分の2について稅額の8割が猶予の対象ですが、この制度を使っても相続した株式の稅額のうち実質的に53%しか猶予されず、事業承継に二の足を踏むことも多かった點にあります。そこで、2018年稅制改正案では、次のようなポイントで事業承継をスムーズに行えるよう支援する計畫です。
- ?猶予できる株數を「全株」に引き上げることで、贈與稅の全額?相続稅の株式評価対象分の全額が猶予されるようにする。
- ?猶予條件を緩和する。現在は5年間で8割の雇用を維持できなければ、全額を納稅する必要がありましたが、雇用計畫策定などの條件をつけた上で雇用要件は原則として撤廃されます。
- ?5年間の事業継続期間が終了した後に、贈與時點の評価額より低い金額で譲渡(M&A)した場合や、破産、精算、合併、株式交換等があったときは、その時點の評価額で相続稅を再計算し、超える部分の猶予稅額が免除されます。改正で自主廃業の場合も同様に取り扱われる予定です。
- ?親族以外の経営者や外部の企業がM&Aにより経営を引き継いだ場合の登録免許稅や不動産取得稅の軽減なども検討します。
こうした一連の改正により、現在は年500件程度にとどまる事業承継稅制の適用件數を2,100件以上に増やしたい考えです。
現行の相続稅の優遇制度
稅制が改正されるまで、現行の相続稅の優遇制度が適用されますので、そのポイントをご紹介します。自社株式等の相続稅の納稅猶予額は、経営承継相続人が納稅猶予の適用対象となる自社株式等の20%相當額のみを相続したものとして計算した相続稅額を引いた金額とされます。ただし、納稅猶予額は他の相続人の取得財産は変わらないことが條件となります。具體的には次の手順で計算します。
- (1)通常の相続稅額の計算
相続稅の課稅財産の合計から基礎控除を引いた金額を、実際に相続した財産ではなく、法定相続分によって取得したものとみなして相続稅の総額を計算します。次に、実際に各人が取得した財産の割合で按分して各人の相続稅額を算出します。 - (2)経営承継相続人以外の相続人の相続稅の確定
この段階で経営承継相続人以外の相続稅額は確定します。それは、経営承継相続人以外の相続人の相続稅には、非上場株式等の80%減額による稅額減少の影響は及ばないからです。 - (3)経営承継相続人の納稅猶予額の計算
(1)経営承継相続人は納稅猶予対象株式等のみを相続するものとして、他の相続人の取得財産を合算して相続稅額を計算します。株式等の評価額から経営承継相続人が負擔する債務(葬式費用含む)を控除して計算します。次の(2)も同様です。債務はまず「その他の財産」から控除します。
(2)経営承継相続人は納稅猶予対象株式等の20%相當額のみを相続したものとして、他の相続人の取得財産と合算して納稅額を計算します。
(3)上記(1)-(2)=経営承継相続人の納稅猶予額となります。
【事例】2900萬円納付すべきところ、1779萬円余りで済むケース
事例で計算してみます。自社株式全て納稅猶予の適用対象であるとします。財産は自社株式の評価額1億円、その他の財産2億円、合計3億円となります。相続人2人、會社を相続しない相続人Aがその他の財産1億5,000萬円、経営承継相続人Bが1億円とその他財産5,000萬円で、1億5,000萬円を相続したものとします。
自社株式1億円+その他の財産2億円=3億円
配偶者はいない。子2人
相続人Aその他財産1億5,000萬円
経営承継相続人B1億円+その他財産5,000萬円
- (1)通常の相続稅額の計算
3億円から基礎控除(3,000萬円+600萬円×2人=4,200萬円)を差し引き、その法定相続分は1人當たり1億2,900萬円となります。これに相続稅を乗じて計算すると1人當たり3,460萬円となります。相続人Aの稅額は3,460萬円で確定です。 - (2)経営承継相続人Bが自社株式のみを取得した場合の相続稅額
Bが自社株式のみを相続したとすると1億円となります。これに相続人Aの1億5,000萬円の財産を加算して相続稅を計算すると相続稅の総額は4,200萬円となり、これを全體の財産に対するBの自社株式の評価額で按分すると、Bの相続稅額は1,968萬円となります。 - (3)経営承継相続人Bが自社株式の20%相當額のみを取得した場合の相続稅額
Bが自社株式の20%だけを相続したとすると2,000萬円となります。これに相続人Aの1億5,000萬円の財産を加算して相続稅を計算すると、相続稅の総額は2,440萬円となり、これを全體の財産に対するBの自社株式の20%の評価額で計算すると、相続稅は287萬円強となります。 - (4)納稅猶予額の計算
(2)の経営承継相続人Bの相続稅額1,968萬円から、(3)のBの相続稅額約287萬円を引いた約1,681萬円弱が納稅猶予額となります。 - (5)各人の納付稅額
結果として経営承継相続人Bの納付稅額は3,460萬円-1,681萬円となり、約1779萬円が納付稅額となります。このように通常の納付稅額よりも非常に低い相続稅額の納付で會社の経営承継が可能になります。