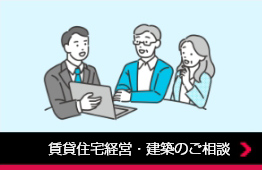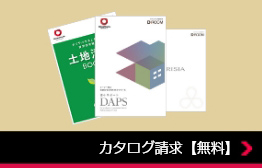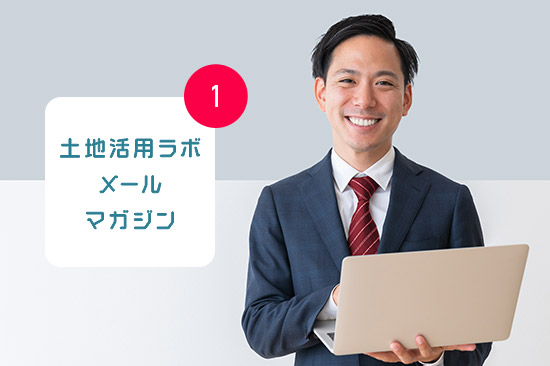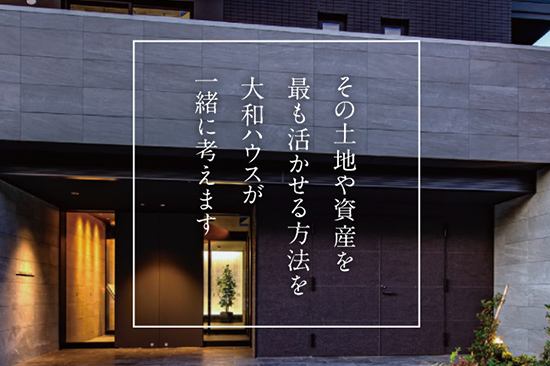コラム vol.544
コラム vol.544キャップレートの動向と長期國債金利とのイールドギャップ
公開日:2025/04/10
土地活用での賃貸住宅建築、また商業施設建築など、あるいは分譲型の賃貸用住宅を購入する等、何らかの不動産投資を行う際には、「どれくらいの利回りを目標とするか」は重要です。しかし、その際、「現狀ではどれくらいの利回りが標準的なのか」等は、なかなかわかりにくいものです。
そこで、多くの投資家が目安としているのが、キャップレートです。キャップレートは、NOI(Net Operating Income:純収益)÷投資金額で算出されます。還元利回りと同じ計算ですが、キャップレートの算出は、「どれくらい期待するか」あるいは「どれくらい求めるか」という投資家へのアンケート調査が主ですので、「今の投資家が利回り目線」を示したものと言えます。
しかしながら、不動産は獨自固有性が強い投資ですので、數字そのものが、ズバリ當てはまるわけではありません。そのため、「傾向」という感じで見ておくと良いと思います。
今回は、最新の賃貸住宅のキャップレートの動向を解説します。
キャップレートの動向
キャップレートという考え方が日本に持ち込まれ始めたのは2000年になる少し前、そして業界に広まったのはミニバブル期(2007年~2009年)以降、また広く一般の投資家に広まったのは2013年以降です。
それでは、昨今のキャップレートの狀況はどうなっているのでしょう。ここでは、賃貸住宅におけるキャップレートを例に挙げて傾向を見ておきましょう。
図1:賃貸住宅の期待利回り(CAPレート)の推移
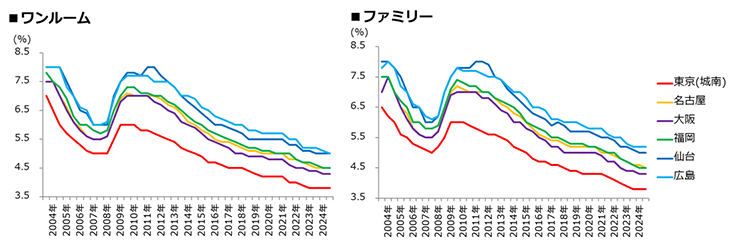
一般財団法人 日本不動産研究所「不動産投資家調査」より作成
図1は、2004年以降20年間の全國主要都市の賃貸住宅(ワンルーム?ファミリー)のキャップレートの推移を示しています。この推移を見ると、リーマンショックでキャップレートは上昇しましたが、その後、特に2013年以降は全國的に低下が続いています。地域別にみれば、東京は2010年ごろから低下傾向、大阪、名古屋、福岡は2012年ごろから、他の地域は金融緩和が進んだ2013年以降に低下しており、どの地域もこの調査が始まった(1999年)以降、最低となっています。
冒頭で述べたようにキャップレートは投資家の期待利回りのことです。仮に賃料が橫ばいとすれば、キャップレートが低下しているということは価格上昇を意味します。つまり、賃貸住宅への投資としての価格は、最高水準にあるということになります。投資家の不動産投資への意欲が極めて高いことうかがえます。
また、直近1年のキャップレートは橫ばいの地域が多くなっていますが、賃料は上昇している中でのキャップレート橫ばいですので、それだけ、投資としての賃貸住宅の価格が上昇しているということになります。
キャップレートとリスクフリーレートの、イールドギャップ
図2は、2006年以降の東京城南地域における賃貸住宅(ワンルーム)のキャップレートの推移(=青線)と10年物國債の利回りの推移(=オレンジ線)とその差(=點線)を示しています。どの地域でも、同様の傾向にありますので、ここでは東京(城南エリア)を取り上げます。
図2:賃貸住宅のキャップレート(東京(城南)1R)と10年物國債の比較
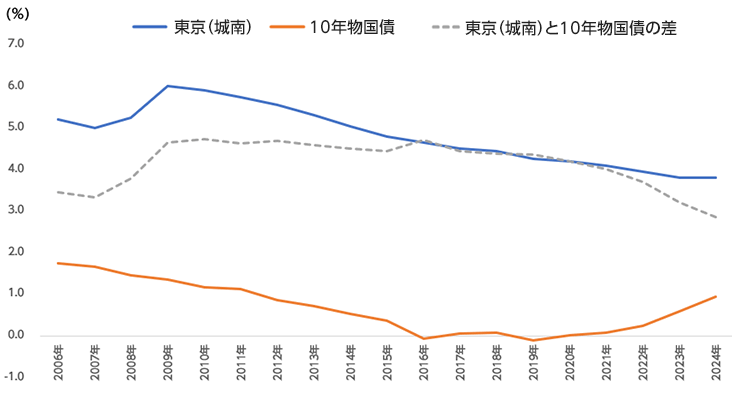
一般財団法人 日本不動産研究所「不動産投資家調査」?財務省より作成
キャップレートを理論上分解すれば、「キャップレート=リスクフリーレート(ここでは10年物國債)+立地リスクプレミアム+不動産投資リスク」となります。ここ(グラフ)では、同一立地(=東京城南)ですので、キャップレートと10年物國債の利回りの差をとれば、投資家が考える「不動産投資に対するリスクの大きさ」の変化がわかります。
グラフの點線をみれば、國債金利が上昇した2022年以降にもキャップレートは低下、もしくは橫ばいとなっていますので、昨今は「不動産投資に対するリスクが低下している」と考える投資家が増えていることがわかります。
キャップレートの動向
このように、不動産投資に金融商品と同じような考えを持ち込めば、不動産投資に対する要求利回りは、安定的に得ることができる利回り=リスクフリーレート※(不動産投資は基本的に長期投資ですので、一般的は長期〔10年物〕國債の利率を適用)に、不動産投資リスクを加味したものと言えます。
※リスクが最小でリスク?フリーに近い金融商品から得られる利回り 紹介したキャップレート調査「賃貸住宅の期待利回り(CAPレート)の推移」は2024年10月実施で、このころの長期國債金利は1%前後で推移していました。
しかし、2025年3月に入り1.5%を超える水準となっており、0.5%程度上昇しています。賃料も上がっていますので、この長期國債金利の上昇幅がそのまま、キャップレートの上昇につながるとは思いませんが、多少の上昇可能性がでてきたと言えるでしょう。