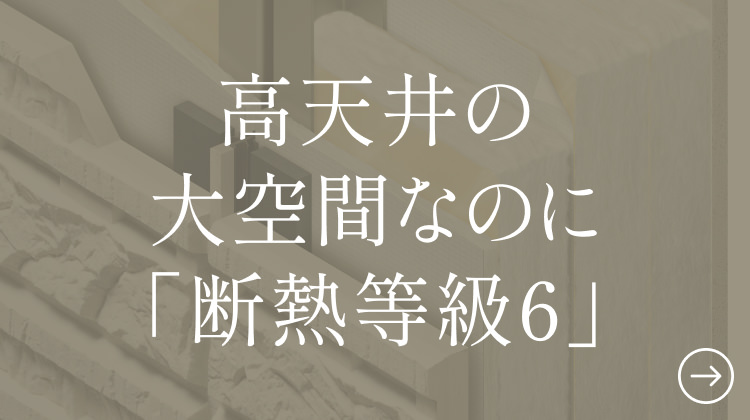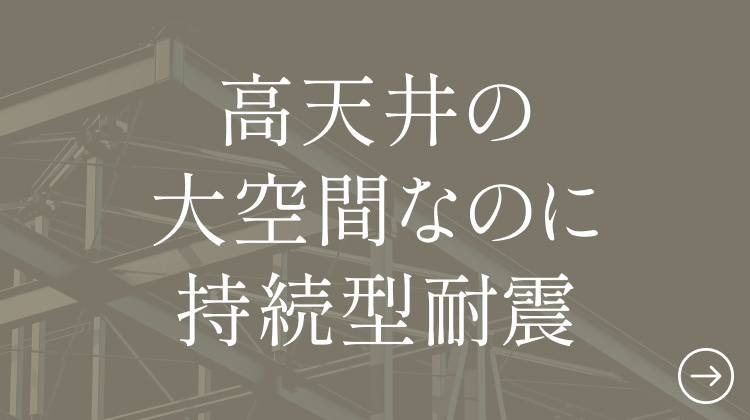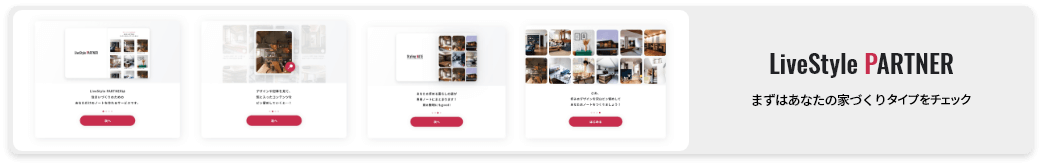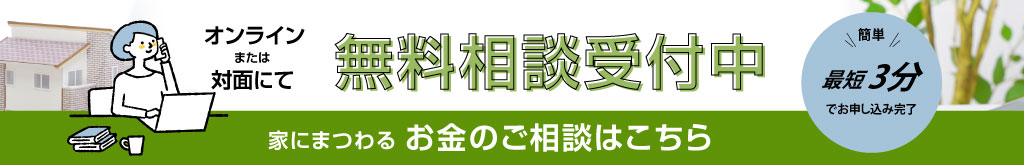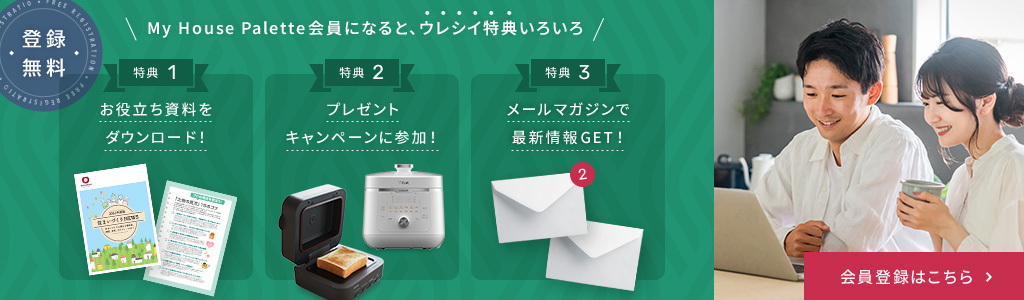「インフレーション(インフレ)」とは物の値段が上がり、お金の価値が下がることを指します。
例えば、卵の値段を思い出してみてください。
JA全農(nóng)たまご株式會(huì)社が発表している相場(chǎng)情報(bào)によると、
2020年1月時(shí)點(diǎn)では卵1kgの値段は170円でしたが、
2025年1月時(shí)點(diǎn)では約1.5倍の258円まで値上がりしました。
以前は200円出せばお釣りがきていたのに、今では200円では買(mǎi)えないということです。
つまり、同じ200円というお金の価値は5年前よりも下がっているということになります。
これが、インフレです。インフレ時(shí)代といわれる今、インフレに左右されず將來(lái)に向けて資産を築くために
必要な資産運(yùn)用の方法についてご説明していきます。
6つの資産運(yùn)用の特徴
今回は、代表的な6つの資産運(yùn)用の特徴について觸れていきます。
預(yù)貯金
はじめに身近な預(yù)貯金についてご説明していきます。預(yù)貯金には元本保証があるため、預(yù)けた元本が將來(lái)受け取る時(shí)に減らないことを金融機(jī)関が約束しています。仮に、預(yù)けていた金融機(jī)関が経営破綻に陥ったとしても、預(yù)貯金は預(yù)金保険制度で一定範(fàn)囲內(nèi)は保護(hù)されるため安全性の高い資産といわれています。なお普通預(yù)金の金利は、約0.2%となっています。(2025年9月現(xiàn)在:三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行データ參考)
メリット
- 元本保証あり
- 預(yù)金保険制度により一定額まで保護(hù)
- 安全性が高い
デメリット
- 金利が低く、インフレに弱い
- 資産が増えにくい
投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をまとめ、投資の専門(mén)家が株式や債券、不動(dòng)産などに分散投資して運(yùn)用する金融商品です。運(yùn)用の成果は、投資額に応じて投資家に還元されますが、元本が保証されているわけではなく、損失が出る可能性もあります。少額から始められ、個(gè)人では直接手が屆きにくい銘柄にも投資できる點(diǎn)や、運(yùn)用を?qū)熼T(mén)家に任せられるため個(gè)人への負(fù)擔(dān)が少ない點(diǎn)は大きな魅力です。忙しい方や投資初心者にとっては、売買(mǎi)の手間が少なく、資産運(yùn)用の入り口として取り入れやすい商品といえるでしょう。中でも、日経平均株価などの指數(shù)に連動(dòng)して動(dòng)く「インデックスファンド」は、低コストで分散投資が可能な選択肢として人気があります。
メリット
- 少額から分散投資が可能
- 専門(mén)家に運(yùn)用を任せられる
- 多様な資産に投資が可能
デメリット
- 元本保証なし
- 運(yùn)用成果によって損失が出る可能性
図1:投資信託の仕組み

株式
株式會(huì)社に資金を出資している証明として、株主に対して発行される有価証券を株式と呼びます。株主が株式會(huì)社へ出資した資金は、會(huì)社が存続する限り払い戻しされないため、株主が株式を換金する場(chǎng)合には、株式市場(chǎng)で売卻することになります。 株式投資とは、將來(lái)性のある企業(yè)、良い商品やサービスを提供している企業(yè)を支援することによって利益を得ることを意味しており、その會(huì)社に出資して資金面で応援するという楽しみや、會(huì)社を育てて、経済や社會(huì)の発展に寄與するという社會(huì)的な意義も持っています。 株式投資の特徴としては ①値上がり益(キャピタルゲイン〈株価が買(mǎi)った時(shí)よりも売った時(shí)の方が値上がりすることで、得られる売卻益〉) ②配當(dāng)(インカムゲイン〈會(huì)社が得た利益を株主へ還元すること〉)③株主優(yōu)待(自社製品やサービスなどを提供すること) などが挙げられます。一方で、元本保証はなく、発行企業(yè)の経営破綻や株価の値下がりのリスクも伴うので、投資対象の株式會(huì)社についてよく調(diào)べることが大切です。
メリット
- 値上がり益や配當(dāng)が狙える
- 株主優(yōu)待がある
- 経済?企業(yè)成長(zhǎng)に貢獻(xiàn)
デメリット
- 価格変動(dòng)リスクが大きい
- 元本保証なし
- 企業(yè)分析が必要
NISA
NISAは、少額投資非課稅制度のことを指します。通常、預(yù)金利息や売卻益、配當(dāng)など、投資で得た利益には20.315%の稅金が課せられますが、NISA口座で株式や投資信託などを購(gòu)入すると、一定の投資枠に対する利益が非課稅となります。例えば20萬(wàn)円の売卻益があった場(chǎng)合、通常の口座では手元に受け取ることができる利益は稅引き後15萬(wàn)9,370円となりますが、NISA口座であれば20萬(wàn)円を受け取ることができるということです。
2024年1月からスタートした「新NISA制度」は、これまでの「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」を一本化し、非課稅での投資をより柔軟かつ長(zhǎng)期的に行える制度へと生まれ変わりました。新制度では、「つみたて投資枠」と「成長(zhǎng)投資枠」の2つの投資枠が設(shè)けられ、年間最大360萬(wàn)円(つみたて投資枠120萬(wàn)円+成長(zhǎng)投資枠240萬(wàn)円)まで非課稅で投資することが可能です。従來(lái)は併用できなかった2つの枠を同時(shí)に利用できる點(diǎn)が大きな特徴です。
「つみたて投資枠」は、一定の條件を満たした長(zhǎng)期?積立?分散投資向けの投資信託等が対象で、毎月一定の金額を積立方式で投資します。一方、「成長(zhǎng)投資枠」では、上場(chǎng)株式やETF(上場(chǎng)投資信託)など、より幅広い商品に一括投資または積立で投資することができます。
また、従來(lái)5年や20年と制限されていた非課稅保有期間が「無(wú)制限」となりました。さらに、制度自體も恒久化されたため、今後制度が廃止される心配がなく、安心して長(zhǎng)期投資を続けられます。非課稅投資の上限額としては、1人あたり「生涯投資枠1,800萬(wàn)円」が設(shè)定されており、成長(zhǎng)投資枠はその內(nèi)最大1,200萬(wàn)円まで投資できます。つみたて投資枠のみで1,800萬(wàn)円を使い切ることも可能です。
なお、舊NISA制度による買(mǎi)い付けは2023年12月で終了し、「ジュニアNISA」も同時(shí)に廃止されました。ただし、これまでに購(gòu)入したジュニアNISAの資産は、18歳になるまで引き続き非課稅で保有できます。
メリット
- 運(yùn)用益?配當(dāng)などが一定枠內(nèi)非課稅
- 少額投資に有利
デメリット
- 投資対象のリスクはそのまま
- 非課稅枠に上限がある
表1:新NISAについて

出典:NISAを知る:NISA特設(shè)ウェブサイト(金融庁)
※ ①整理?監(jiān)理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
債券
債券は、資金調(diào)達(dá)をしようとする國(guó)や地方公共団體、企業(yè)などの発行體が多數(shù)の投資家から資金を借り入れる際に発行する、いわば「借用証書(shū)」です。購(gòu)入した後は、定期的に利子を受け取り、満期時(shí)點(diǎn)で額面金額が償還される仕組みになっています。
また、満期以前の換金は中途換金によって行います。ただし、中途換金は、その時(shí)點(diǎn)の市場(chǎng)価格によるのが原則です。市場(chǎng)価格は日々変動(dòng)しますので、購(gòu)入時(shí)點(diǎn)の価格よりも、値上がりしていることもあれば、値下がりしていることもあります。
代表的なものに、國(guó)が発行している個(gè)人向け國(guó)債があります。5年固定タイプの金利は、1.12%(稅引き後は約0.89%)となっていますので、仮に100萬(wàn)円國(guó)債を保有した場(chǎng)合、稅引き後毎年約8,900円、5年間で合計(jì)約44,500円の利息を受け取ることができます。ただし、個(gè)人向け國(guó)債は1年以內(nèi)の中途換金ができないので注意が必要です。
メリット
- 利子収入が得られる
- 原則満期まで保有すれば元本が返ってくる
デメリット
- 中途換金で元本割れの可能性あり
- 金利変動(dòng)リスク
不動(dòng)産
資産の種類として不動(dòng)産(自宅)も挙げることができます。不動(dòng)産は、居住するための場(chǎng)所であると同時(shí)に、資産としての価値を持ちます。住宅ローンを完済すれば、その後は家賃に相當(dāng)する支出が発生しないため、長(zhǎng)期的に見(jiàn)て大きな経済的メリットを得られます。特に老後までに返済を終えていれば、住居費(fèi)の負(fù)擔(dān)を大幅に抑えられ、年金生活でも安定した暮らしを送りやすくなります。
さらに、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除や相続時(shí)における評(píng)価額の圧縮効果も期待できます。不動(dòng)産は現(xiàn)金などの他の資産と比べて相続稅評(píng)価額が低く算定される場(chǎng)合があるため、結(jié)果的に相続稅の負(fù)擔(dān)を抑えられる點(diǎn)も特徴といえるでしょう。一方で、購(gòu)入にはまとまった資金が必要であり、住宅ローンの返済や固定資産稅、修繕費(fèi)などの維持管理コストも継続的に発生する點(diǎn)には注意が必要です。
資産運(yùn)用の観點(diǎn)からは、不動(dòng)産は「守りの資産」といわれています。インフレ時(shí)には物価と連動(dòng)して不動(dòng)産価格が上昇する可能性があります。実際、近年では新築住宅や分譲マンションの価格が高騰しており、その影響で中古住宅市場(chǎng)の価格も上昇傾向にあります。しかし不動(dòng)産を資産として保有していることで価格上昇の影響を受けずにすむため、インフレ対策としての効果も発揮します。また、転勤などで引っ越しが必要になった場(chǎng)合でも、賃貸に出して家賃収入を得たり、売卻して新たな住まいに住み替えたりと、ライフスタイルの変化に応じた柔軟な選択ができる點(diǎn)も魅力です。
メリット
- 資産として殘り、売卻も可能
- 家賃が不要になる
- 稅制優(yōu)遇や稅務(wù)対策効果あり
- インフレ対策になる
デメリット
- 購(gòu)入時(shí)にまとまった資金が必要
- 維持費(fèi)や固定資産稅が発生
ここで、主要6資産のメリット、デメリットについて、表に整理してみましょう。
表2:主要6資産の比較表
| 資産種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 預(yù)貯金 |
|
|
| 投資信託 |
|
|
| 株式 |
|
|
| NISA |
|
|
| 債券 |
|
|
| 不動(dòng)産(自宅) |
|
|
インフレに左右されない資産運(yùn)用とは
インフレ時(shí)代を生きる私たちにとって、資産を守りながら増やすことはとても大切です。そのためには、全體のポートフォリオを考えながら、「増やす資産」と「守る資産」をバランスよく持つことがポイントです。
「増やす資産」とは、投資信託?株式?NISAなど、元本保証はないものの、比較的高いリターンを狙える運(yùn)用資産を指します。これらの金融商品は、経済成長(zhǎng)や企業(yè)の業(yè)績(jī)向上に連動(dòng)して価値が上昇する可能性があるため、長(zhǎng)期的に見(jiàn)た場(chǎng)合インフレに強(qiáng)い資産形成が期待できます。ただし、リターンがある分、価格の変動(dòng)リスクや元本割れのリスクも存在します。
例えば、株価が急落するような局面では、資産が一時(shí)的に大きく目減りする可能性も否定できません。そのため、「増やす資産」を運(yùn)用する際は、投資先を分散させることが大切です。具體的には、國(guó)內(nèi)外の株式や債券、投資信託など、複數(shù)の資産クラスや地域に分散して投資することで、一部の資産が値下がりしても他の資産で補(bǔ)うことができ、リスクを抑えながら資産を増やしていくことが可能になります。
一方で、「守る資産」は、預(yù)貯金や國(guó)債などの債券、不動(dòng)産など、資産価値が大きく変動(dòng)しにくい安定型の資産です。これらはリターンこそ比較的控えめですが、安全性が高く、まとまった金額を資金化することも可能であることが大きなメリットです。
特に、注目したいのが不動(dòng)産(自宅)を持つという選択です。インフレが進(jìn)む中で、賃貸住宅に住み続ける場(chǎng)合、將來(lái)的に家賃が上昇していくリスクがあります。家賃は物価の影響を受けやすいため、インフレが進(jìn)行すると、住居費(fèi)負(fù)擔(dān)は大きくなります。一方で、物件を購(gòu)入し住宅ローンを活用した場(chǎng)合、支出が固定されるというメリットがあります。特に固定金利の住宅ローンの場(chǎng)合、返済額は変わりません。これはインフレによってお金の価値が下がっていく局面において、返済負(fù)擔(dān)が軽くなる効果も期待できます。
さらに、住宅ローンを組む際は、団體信用生命保険(団信)に加入することが一般的で、ご自身に萬(wàn)が一のことがあった場(chǎng)合には殘債が免除されるため、ご家族のために住まいを守れる安心感も得られます。
住宅購(gòu)入のタイミングはインフレ率と金利の動(dòng)向を見(jiàn)極める必要がありますが、このように、不動(dòng)産(自宅)を含めた資産全體のバランスを見(jiàn)直すことで、インフレに左右されない資産運(yùn)用が可能になります。
まとめ
今回は、インフレ時(shí)代に備える6つの資産運(yùn)用の特徴についてご説明しました。 中でも人生で一番大きな買(mǎi)い物といわれる不動(dòng)産の購(gòu)入は、迷いや不安を感じる方が多いかもしれません。一方でインフレによる家賃の上昇リスク等を考えると、住まいを持つことは將來(lái)への備えとして有力な選択肢の一つです。將來(lái)どこで、どんな暮らしをしたいのかを考えることは、資産形成の第一歩でもあります。これを機(jī)に、ご自身のライフプランやポートフォリオの見(jiàn)直しを進(jìn)めてみてはいかがでしょうか。ぜひその際には専門(mén)家の力を借りて、大切な將來(lái)に向けたライフプランの作成をしながら検討していただければと思います。

執(zhí)筆者
山田健介
FPplants株式會(huì)社 代表取締役社長(zhǎng)
住宅メーカーから金融機(jī)関を経て「お客さまにお金の正しい知識(shí)や情報(bào)をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う會(huì)社を設(shè)立。現(xiàn)在は全國(guó)のFPを教育する傍ら、執(zhí)筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。
※掲載の情報(bào)は2025年9月現(xiàn)在のものです。內(nèi)容は変わる場(chǎng)合がございますので、ご了承ください。
関連リンク