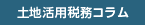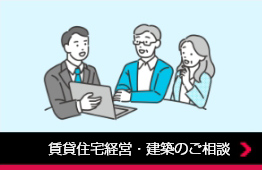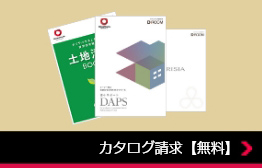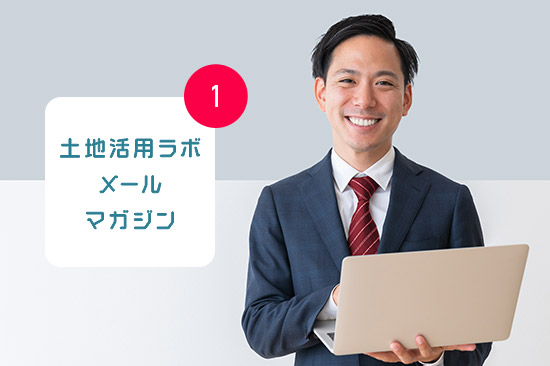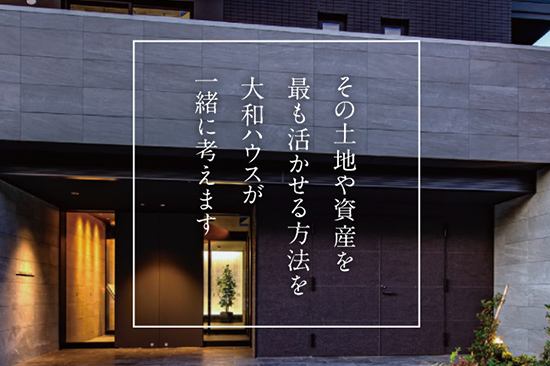コラム vol.551
コラム vol.551賃貸住宅経営における「工法の違い」軽量鉄骨と重量鉄骨の違いとは
公開(kāi)日:2025/05/30
賃貸住宅を建築する際は、「木造(W造):主要な支えが木材で建築されている構(gòu)造」「鉄骨造(S造):建物の骨組みに鉄骨を用いられる構(gòu)造」「鉄筋コンクリート造(RC造):鉄筋とコンクリートで造られた構(gòu)造」の3種類の工法が用いられることが一般的です。中でも鉄骨造は、木造よりも耐久性、耐震性などに優(yōu)れていることから、多くの賃貸住宅で用いられている構(gòu)造ですが、鋼材の厚みによって、軽量鉄骨と重量鉄骨に分かれています。「軽量鉄骨:鋼材の厚みが6mm未満(一戸建てや3階建てまでの集合住宅の場(chǎng)合が多い)」「重量鉄骨:鋼材の厚みが6mm以上(店舗併用や3階建て以上の賃貸住宅の場(chǎng)合が多い)」に分かれます。
一般的な住居に多い木造とマンションに多い鉄筋コンクリートについては、見(jiàn)た目にもわかりやすく、違いも認(rèn)識(shí)しやすいと思いますので、ここでは、外観を見(jiàn)ただけでは違いが分かりにくい、軽量鉄骨と重量鉄骨の違いについて紹介します。
軽量鉄骨と重量鉄骨は使用する鋼材の厚みによって分類されますが、その違いを簡(jiǎn)単に紹介します。
表1:軽量鉄骨と重量鉄骨の違い
| 軽量鉄骨 | 重量鉄骨 | |
|---|---|---|
| 鉄骨材(鋼材)の厚み | 6mm未満 | 6mm以上 |
| 主な建築用途 | 戸建て住宅?低層賃貸住宅?小型店舗など | マンション?3階建て以上の賃貸住宅?商業(yè)施設(shè)など |
| 法定耐用年數(shù) | 19~34年 | 34年 |
| 主に採(cǎi)用される工法?構(gòu)造 | プレハブ工法 鉄骨軸組工法(ブレース工法) |
鉄骨ラーメン構(gòu)造 鉄骨ユニット工法 |
機(jī)能としての違い
鉄骨材の厚みの違いは、いくつかの機(jī)能的な違いをもたらします。まず、重量鉄骨は梁が太いため、大きな空間を作ることが可能です。そのため、自由なレイアウトがしやすく、店舗や事務(wù)所に向いているといえます。店舗を併用した賃貸住宅には重量鉄骨が向いているといわれる所以です。また、強(qiáng)度が高く、鉄骨柱の本數(shù)が少なくて済むため、リフォ-ム時(shí)に間取りを変更しやすいともいえるでしょう。
また、地震時(shí)の揺れにも強(qiáng)いことから、3階建て以上の賃貸住宅は重量鉄骨造が適しているともいわれています。よって、都市部などでの狹小土地でも、法的に問(wèn)題がなければ高さのある住居を建てることも可能となります。柱や梁が太く壁が厚いことから、防音性にも優(yōu)れています。賃貸住宅やマンションでは、騒音トラブルは大きな問(wèn)題のひとつですので、防音性能に優(yōu)れているのは、賃貸住宅ではメリットになりえます。
ただし、重量鉄骨は軽量鉄骨よりも建築コストは高くなります。また、建物全體も軽量鉄骨よりも重くなるため、地盤(pán)補(bǔ)強(qiáng)が必要になるケースもあり、あくまで、長(zhǎng)期的な賃貸住宅経営として収益バランスを見(jiàn)ながら柔軟に判斷することが大切です。
対して軽量鉄骨は、鉄骨部材の薄さから、3階建てまでの低層住宅の建築に適しているといわれていますが、最近では技術(shù)の向上により軽量鉄骨の3階建て賃貸住宅も多く見(jiàn)かけるようになりました。
軽量鉄骨は、施工性にも優(yōu)れ、重量鉄骨に比べると建築コストも低いのが大きなメリットといえます。建築コストは木造よりも高くなりますが、重量鉄骨や鉄筋コンクリートよりは低く、デザイン性の高い賃貸住宅を建てることができれば、ご入居者の評(píng)価も得られやすく、バランスの良い構(gòu)造だといえるでしょう。賃料を少しでも抑えたい若い世代や、デザインを重視するご入居者を?qū)澫螭趣筏抠U貸住宅であれば、検討する余地がありそうです。工期が短いのも特徴で、賃貸住宅経営の視點(diǎn)からも、早期の入居によって収益化も早くなります。
あくまで経営計(jì)畫(huà)に即した工法を選ぶ
工法上の機(jī)能的な違いを認(rèn)識(shí)した上で、どのような工法を選ぶのかは、あくまで経営計(jì)畫(huà)や、賃貸住宅を建てる目的、考え方によります。例えば、賃貸住宅は大切な資産であり、資産価値を保ちたいと考えるならば、できる限り資産価値の下がりにくい重量鉄骨造を選択することも考えられますし、建築コストを抑えて、できる限り賃料を低く提供したいと考えるならば、建築コストの低い工法を選択すべきでしょう。 昨今の軽量鉄骨による賃貸住宅は、斷熱性、耐震性、防音性も向上していますので、長(zhǎng)期的な賃貸住宅経営の視點(diǎn)から検討することが重要です。
減価償卻を考慮した選択を
賃貸住宅の工法を決めるにあたって、押さえておきたいのが、減価償卻の年數(shù)です。「構(gòu)造の種類」によって、「法定耐用年數(shù)」が異なるため、経費(fèi)として減価償卻費(fèi)を計(jì)上できる金額や期間の長(zhǎng)さが違うからです。軽量鉄骨と重量鉄骨の法定耐用年數(shù)と、定額法償卻率は、以下の通りです。
| 構(gòu)造 | 耐用年數(shù) | 定額法償卻率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 3mm以下 | 19年 | 0.053% |
| 3mm超4mm以下 | 27年 | 0.038% | ||
| 4mm超 | 34年 | 0.030% | ||
| 重量鉄骨造 | 34年 | 0.030% | ||
3ミリ以下の軽量鉄骨の場(chǎng)合、減価償卻費(fèi)を計(jì)上できる年數(shù)が19年となりますので、比較的短期で減価償卻費(fèi)の計(jì)上が終わってしまいます。一方で重量鉄骨造の場(chǎng)合、法定耐用年數(shù)は34年と長(zhǎng)くなっています。そのため、長(zhǎng)期的に減価償卻費(fèi)の計(jì)上が可能であり、長(zhǎng)期的な経営に向いているといえます。なお、法定耐用年數(shù)を過(guò)ぎると減価償卻費(fèi)の計(jì)上ができなくなり、利益が増加してしまいますので、所得稅などの稅負(fù)擔(dān)が増えてしまうことには注意が必要です。
賃貸住宅経営を行う際には、木造、鉄筋コンクリートを含む、どの工法で建てるかという問(wèn)題は、長(zhǎng)期的な収益に直結(jié)する問(wèn)題です。また、建築會(huì)社やハウスメーカーによっても得意な工法がありますので、専門(mén)家に相談しながら、自身の賃貸住宅経営計(jì)畫(huà)に沿った工法を選ぶようにしましょう。