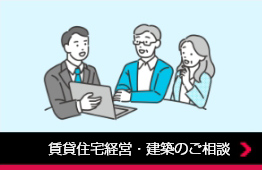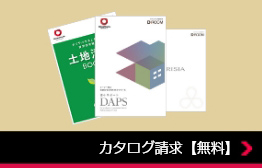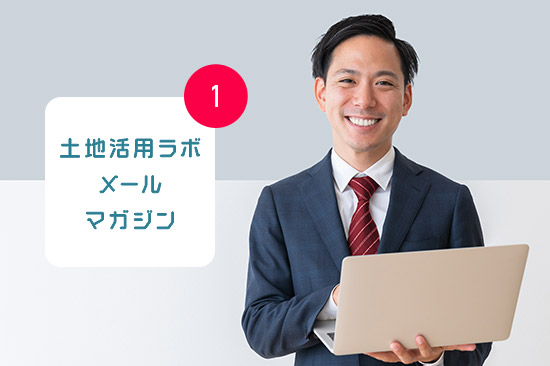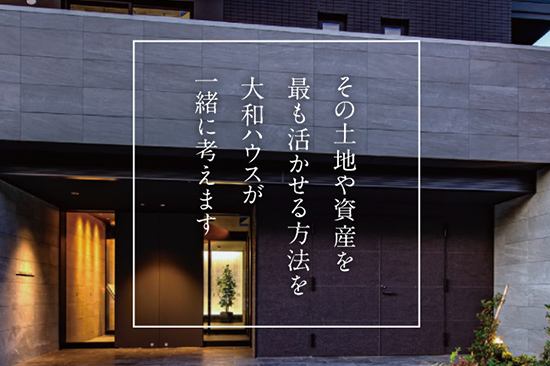コラム vol.450
コラム vol.450人口動態(tài)の変化に伴う賃貸住宅ニーズの変化
公開日:2023/04/28
POINT!
?2022年の日本の総人口は1億2494萬7千人で、2011年以降12年連続の減少となった。一方、世帯數(shù)は増加し、全世帯の38.1%が単獨世帯となった
?大都市に限れば、単獨世帯の約7割が賃貸住宅に住んでいる
?賃貸住宅経営では、將來の需要見通しに伴い、住宅に求められるものが変化するため、人口や世帯數(shù)など社會環(huán)境の変化を的確にとらえる必要がある
最新の我が國の人口
総務(wù)省が2023年4月12日に発表した、2022年10月1日時點の日本の総人口は1億2494萬7千人で、この1年間に55萬6千人(-0.44%)の減少となりました。人口のピークは2008年で、2011年以降12年連続の減少となりました。出生數(shù)(79.9萬人)から死亡數(shù)(153萬人)を引いた自然増減が大きくマイナスとなっており、そのことが人口減少につながっています。 また、15歳未満の人口は28.2萬人の減少、総人口に占める割合は11.6%(マイナス0.2ポイント)となり、若年層の人口減少が顕著となっています。県を跨いでの移動が伴う可能性の高い(≒賃貸住宅を利用するであろう)大學(xué)や専門學(xué)校などに進學(xué)する割合は増えているものの、今後は絶対數(shù)が減ります。また就職時における人口も同様に絶対數(shù)は減り続けます。このような人口減少は、賃貸住宅経営にどのような影響を與えるのでしょうか。
増える?yún)g獨世帯
賃貸住宅経営にとって、人口動態(tài)の変化に加えて重要な指數(shù)となるのが世帯數(shù)です。住居は基本的に1世帯、1戸となることが多く、賃貸住宅戸數(shù)に直結(jié)します。
その世帯數(shù)ですが、人口は減少するものの、一貫して増え続けています。その背景にあるのは単獨世帯の増加です。2020年に行われた國勢調(diào)査(2021年11月30日公表)によれば、我が國の全世帯(不詳除く一般世帯)のうち、38.1%が単獨世帯(世帯構(gòu)成員が1人)となっています。それ以前に公表された、國立社會保障人口問題研究所の2018年の推計(ベースは2015年の國勢調(diào)査)では、2031年の単獨世帯の割合が38.1%となっていたため、この推計よりもはるかに速いペースで単獨世帯の割合が増えていることが分かります。
単獨世帯が増える背景には、「高齢夫婦のいずれかの死別」「生涯未婚者數(shù)の増加」「離婚數(shù)の増加」等があるとされていますが、特に未婚者數(shù)が増加傾向にあります。國立社會保障?人口問題研究所の「人口統(tǒng)計資料集(2022年)」によれば、2020(令和2)年の「50歳時の未婚率」は男性が28.25%、女性は17.81%となっており、前回調(diào)査(2015年)と比べると、男性は約3.5ポイント、女性は約2.9ポイント上昇しています。
単獨世帯の賃貸住宅に住む割合
下図は、2020年の國勢調(diào)査より世帯類型別の住まい方について全國と主要都市の狀況を示したグラフですが、単獨世帯の多くは賃貸住宅に住んでいることがうかがえます。
図:単獨世帯の賃貸住宅に住む割合
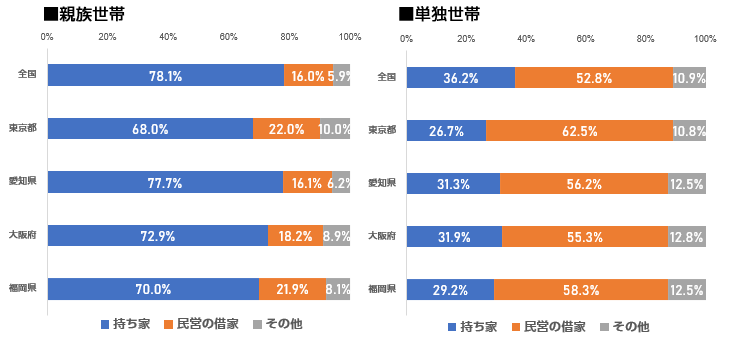
その他:主に公的な賃貸住宅など(以下、その他は公的賃貸住宅としてカウント)
総務(wù)省統(tǒng)計局「令和2年國勢調(diào)査」より作成
全國では単獨世帯のうち、「持ち家」に住む割合が36.2%、殘り63.8%は賃貸住宅に住んでいます。これを大都市に限れば、賃貸住宅に住む世帯の割合は東京都73.3%、愛知県68.7%、大阪府68.1%、福岡県70.8%と約7割の世帯が賃貸住宅に住んでいることが分かります。
つまり、日本で出生した若年層の絶対數(shù)はこれから減少していきますので、賃貸住宅需要を
伴う都道府県を跨ぐ進學(xué)や就職も、長期的に見れば減少することが予測されます。しかし一方で、単獨世帯は大きく増加しており、この分の賃貸住宅の需要増が見込まれることになります。現(xiàn)在、國は少子化対策として、さまざまな施策を計畫していますので、前述した「生涯未婚者數(shù)の増加」「離婚數(shù)の増加」等がどのように変化するのか注目する必要があります。
賃貸住宅に求めるもの
このような將來の需要見通しを考えれば、賃貸住宅に求められるものも変化してくるでしょう。
株式會社リクルートが実施した賃貸契約者動向調(diào)査※によれば、賃貸住宅の設(shè)備における満足度の項目で、「24時間出せるゴミ置き場」が6年連続の1位、2位は宅配ボックス(5位から上昇)と、晝間不在の會社員の方々のニーズを満たすものとなっています。
また、前回調(diào)査(2020年)から大きくジャンプアップしているものとして、「非接觸キー」の満足度が高まり3位となっています。「非接觸キー」は、スマートフォンを利用するタイプやカギを持っているだけで反応して開閉するタイプ(車などに多く搭載)などが主流ですが、最近では「顔認証システム」を?qū)毪筏皮い胭U貸住宅もあり、手ぶらで開閉できるようになっています。
※2021年度賃貸契約者動向調(diào)査(首都圏)、リクルートSUUMOリサーチセンター調(diào)査(公表2022年9月15日)
賃貸住宅の設(shè)備ニーズの変化を的確につかむ
賃貸住宅の設(shè)備ニーズでは、かつてはエアコンやシャワートイレ等が求められ、その後防犯セキュリティ系の設(shè)備の充実、水まわり設(shè)備のグレードなどが求められました。しかし現(xiàn)在では、賃貸住宅に住む方の年齢層、収入も変化し、賃貸住宅ニーズの変化や技術(shù)の進歩に伴い、求められる設(shè)備も変化してきています。
こうした変化を的確にとらえることが、空室が出にくく、家賃下落のしにくい、賃貸住宅経営につながりますので、人口や世帯數(shù)などの社會環(huán)境の変化は確実に把握しておく必要がありそうです。