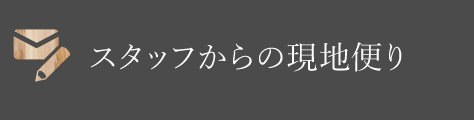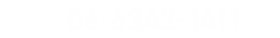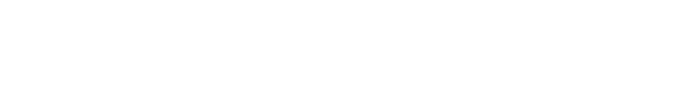一夜建立の伝説を持つ第70番札所?七寶山 持寶院 本山寺
- 更新日:2015年03月23日
- カテゴリ:歴史
正面にはどっしりした八腳の仁王門、國(guó)寶に指定されている
屋根のカーブが美しい寄せ棟造?本瓦葺きの本堂、
昭和59年から平成元年にかけて大修理が行われた大師堂、
室町時(shí)代末期の建築様式を今に伝える鎮(zhèn)守堂など、
広い境內(nèi)には見(jiàn)所がたくさんあります。

屋根のカーブが美しい寄せ棟造?本瓦葺きの本堂、
昭和59年から平成元年にかけて大修理が行われた大師堂、
室町時(shí)代末期の建築様式を今に伝える鎮(zhèn)守堂など、
広い境內(nèi)には見(jiàn)所がたくさんあります。

特に本堂は、外観は京都風(fēng)、內(nèi)部は奈良風(fēng)で、
鎌倉(cāng)時(shí)代の折衷様式の傑作とされています。
鎌倉(cāng)時(shí)代の折衷様式の傑作とされています。
戦國(guó)時(shí)代以降の建築様式が多い讃岐の札所の中で貴重な寺でもあるのです。
馬が盛んに草を食べるように、人間の悪心や欲心、
怒りや悩みなどの煩悩をなくしてくれるというご利益があるそうです。
怒りや悩みなどの煩悩をなくしてくれるというご利益があるそうです。
脇士には薬師如來(lái)と阿彌陀如來(lái)を控えていて、
この阿彌陀如來(lái)には「太刀受けの彌陀」と呼ばれる所以となった伝説を持っています。
兵が境內(nèi)に入ると阿彌陀如來(lái)の右肘から血が滴り落ちていて、
それを見(jiàn)て驚いた兵は退き、寺は戦禍から逃れることができたそうです。
それを見(jiàn)て驚いた兵は退き、寺は戦禍から逃れることができたそうです。
近くには本山寺建立の大師伝説と結(jié)びついた
「枯木の地蔵さん」と呼ばれる古柱が祀られている小さなお堂があるので、
あわせてお參りしてみたいものです。
「枯木の地蔵さん」と呼ばれる古柱が祀られている小さなお堂があるので、
あわせてお參りしてみたいものです。
香川県三豊市?『第70番札所 七寶山 持寶院 本山寺』
當(dāng)分譲地より約190km?車で約3時(shí)間
寫真は平成26年10月撮影
※寫真の掲載につきましては
“四國(guó)八十八箇所霊場(chǎng)會(huì)”から使用の承諾を頂いております。
當(dāng)分譲地より約190km?車で約3時(shí)間
寫真は平成26年10月撮影
※寫真の掲載につきましては
“四國(guó)八十八箇所霊場(chǎng)會(huì)”から使用の承諾を頂いております。