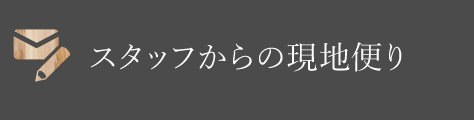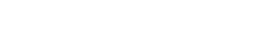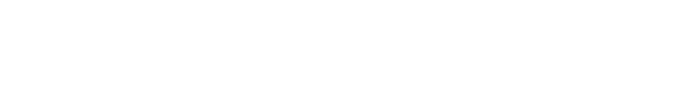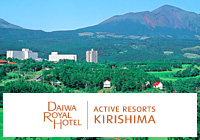霧島市國分 「大穴持神社」
- 更新日:2015年07月02日
- カテゴリ:周辺情報(bào)
遠(yuǎn)く津軽から來た神様は常陸の國の人々が運(yùn)んでくれた
-霧島市國分 「大穴持(オオアナモチ)神社」
霧島市 國分広瀬の國道10號(hào)線沿いに
「大穴持神社」という古社があります。
御祭神は大己貴命(オオナムチノミコト)です。
これは島根県の出雲(yún)大社の大國主命(オオクニヌシノミコト)
の別の神名です。
延喜式にも表せられるように由緒ある神社と言えるでしょう。

また、大穴持神社(オオアナモチ)の社名は
御祭神の大己貴命(オオナムチノミコト)から
きているそうです。
続日本紀(jì)には、
淳仁天皇(764年)の頃、
『十二月、西の方で聲が聞こえた。 雷の音に似ているようで雷ではない。
その時(shí)、
大隅國と薩摩國との堺にあって煙のような雲(yún)が
空を覆って暗くなり、雷光が度々走った。
七日後に空は晴れたが、
信爾(しなに)村(霧島市隼人町あたり)の海に島が現(xiàn)れた。』


その島は神が造った島「神造島(かみつくりしま)」と云われ、
後の光仁天皇の勅命により
奧州津軽山に鎮(zhèn)座されていた「大穴持神社」は、
大地を鎮(zhèn)めるこの地の守神として、
778年(寶亀9年) 神造島沖の小島に遷座されたそうです。
しかし、
地震などで小島が崩壊したため、現(xiàn)在の地へ移されました。
神造島は、辺田小島、弁天島、沖小島から成る三島の総稱で、
現(xiàn)在も、隼人町浜の市の1キロ程沖合にあります。
隼人の地元では、三島(みしま)の愛稱で呼ばれています。
大穴持神社には このような神話があります。
『ある時(shí)、大己貴命が広瀬の畑道を歩いると、突然、
牡の牛が現(xiàn)れ襲ってきたそうです。
驚いた命はとっさに道ばたの麻畑へ逃げ込みました。
牡牛から難を逃れることはできましたが、
逃げ込んだ麻畑にはマムシがウヨウヨいて、
命はマムシから噛まれてしまいました。
手當(dāng)の甲斐もあって、大事には至らなかった』だとさ…。
以來、
大己貴命は、牛やマムシをとても嫌うようになりました。
言い伝えで、
この地區(qū)で牛を飼うと家が栄えないとか??????
大穴持神社から天降川~検校川の辺りまでマムシは
いないとされて神社には、「マムシ除けの砂」があります。
この砂を家の周り撒くと、ヘビやマムシが寄り付かないとか…。


醫(yī)療の神様 または マムシ除けの神様として崇められ、
地元の方々は「おなんじさぁ」と呼んで親しまれています。
大己貴命(オオナムチノミコト)は大國主命(オオクニヌ
シノミコト)の別名神ですので、出雲(yún)大社同様、縁結(jié)びの
ご利益があるかもしれませんね。
奧州津軽山(青森県)に祀られていた大穴持命は、
常陸國(茨城県)の橘氏、宮永氏四人の兄弟、
巖元氏ら一族の手によりこの地へ運(yùn)ばれたそうです。
大穴持神社
霧島市國分広瀬3-1089
■交通アクセス/ロイヤルティー霧島妙見臺(tái)より約14㎞
(車で約32分)
■撮影年月日/全て平成27年5月