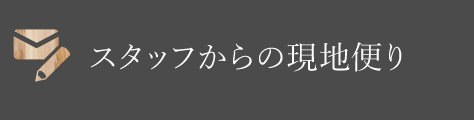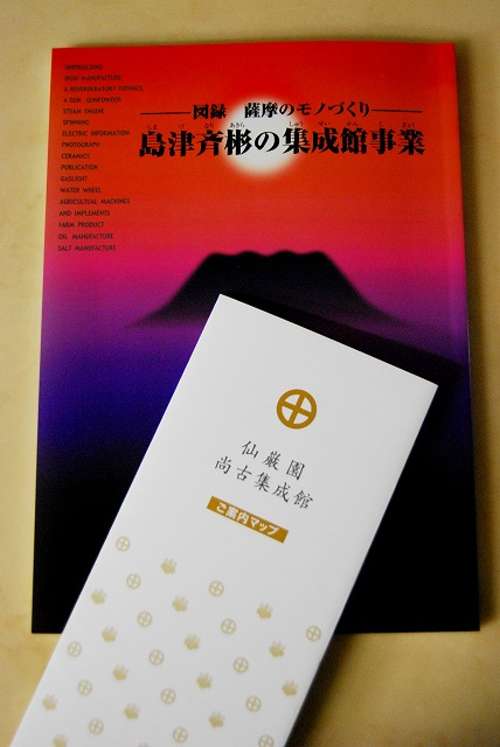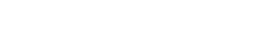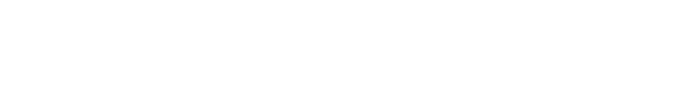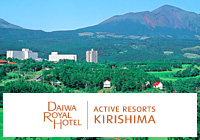日本に技術革新を興した島津斉彬の偉業―鹿児島市「尚古集成館」
- 更新日:2016年03月11日
- カテゴリ:歴史
 19世紀は、
19世紀は、
イギリス、フランスなどの
西歐列強がアジア各國を
植民地化するため進出してきた時代でした。
1840年
東アジア最大の清國は
アヘン戦爭において敗北し、
イギリスの半植民地となりました。
幕末の日本にとっても、西歐列強は脅威でした。

江戸時代末期の薩摩藩は
薩摩國、大隅國、日向國や琉球國を領有していました。
南北1200キロにも及ぶ広大な領域は、
殆どが海に面した海洋國家でもあります。
西歐列強に危懼した第11代藩主、島津斉彬(なりあきら)は、
1852年(嘉永5年)西洋の科學技術を學び導入して、
軍備の近代化を図ろうと、推し進めたのが『集成館事業』です。
 斉彬は島津家別邸「仙巌園」に隣接して、反射爐をはじめ、それに付隨する溶鉱爐、ガラス工場や蒸気機関の製造所などの施設を建設しました。
斉彬は島津家別邸「仙巌園」に隣接して、反射爐をはじめ、それに付隨する溶鉱爐、ガラス工場や蒸気機関の製造所などの施設を建設しました。
これらの工場群は、1200人もの雇用を生み『集成館』と命名されました。
日本の近代工業化の始まりでもあります。
 1863年(文久3年)斉彬の亡くなった後、
1863年(文久3年)斉彬の亡くなった後、
生麥事件に端を発した『薩英戦爭』で、
イギリス軍の圧倒的な軍事力、技術力を思い知らされた薩摩藩は、イギリスとの和平交渉の過程において、藩の軍事力を強化するため軍艦の購入を決めました。
斉彬の遺志を継いだ島津久光(ひさみつ)と藩主の忠義(ただよし)は、西洋の文化や技術の導入を加速させ、1864年(元治元年)6月には藩営の洋學校「開成所」を設け、西洋の技術を學ばせました。
學んだ技術で稼働させたのが、この機械工場である「集成館」です。
1865年(元治2年)3月には、
國禁を犯してまで19名の使節や留學生をイギリスに派遣しました。
 1923年(大正12年)
1923年(大正12年)
「集成館」は「尚古集成館」(しょうこしゅうせいかん)と
名を変え、薩摩藩が行った近代化への事業に関する歴史的資料や、島津家の800年に及ぶ歴史の資料などが集められ、現在に至っています。
150年も前に西洋の工業力を學んだ薩摩。
數々の工業製品の展示には當時のもの作りに対する姿勢がうかがえます。
(殘念ながら館內は撮影禁止でした。)
建築の材料には、鹿児島で古くから塀などに使用されていた、
溶結凝灰巖(ようけつぎょうかいがん)がレンガの代わりに用いられており、
當初から「ストーンホーム」と呼ばれていたそうです。
鹿児島県內に現存する建物の中では、最も古い洋式の工場と言われ、
國の重要文化財に指定されています。
2015年には、
舊集成館に関する史跡が明治日本の産業革命遺産として
世界遺産に登録されています。
 反射爐跡は「仙巌園」の中にあり、基礎部分の石垣が今でも殘っています。
反射爐跡は「仙巌園」の中にあり、基礎部分の石垣が今でも殘っています。
反射爐のレプリカとそこで造られた150ポンド砲のレプリカが鎮座していました。
當時、鶴丸城下に配備された大砲のサイズは、
砲身長4.56メートルで
重量8.3トン、
最大飛距離3,000メートルで、
薩英戦爭に使用されたそうです。


 尚古集成館に隣接して、
尚古集成館に隣接して、
鹿児島の伝統工蕓品の一つ
「薩摩切子」の工場とショップが
「磯工蕓館」。
職人の方々が
それぞれの工程に分かれ、
美しい光を放つ切子を丁寧に作っていました。
薩摩から徳川家へ嫁いだ、
あの「篤姫」も嫁入り道具の一つとして持參したそうです。




『富國強兵』『殖産興業』を掲げた島津斉彬が行った集成館事業は、西郷や大久保らによって、明治の國家政策に流れを継いだに違いありません。
尚古集成館
鹿児島市吉野町9698-1
電話 099-247-1511
※寫真はすべて平成28年3月撮影
※霧島妙見臺より約38㎞