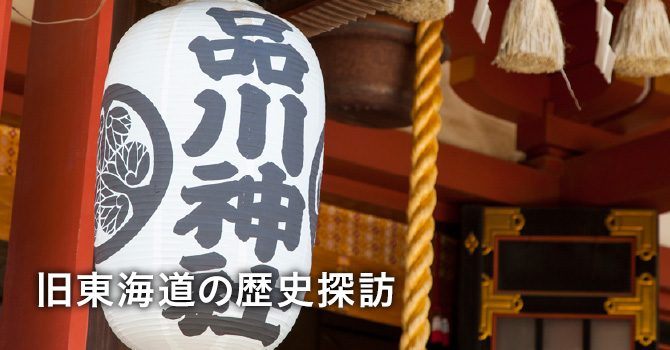
品川の歴史を記憶する鎮(zhèn)守品川神社
第一京浜沿いに立ち並ぶビルや學(xué)校の合間に、突如現(xiàn)れる大きな鳥居。急な階段を軽快に上れば、品川神社の境內(nèi)にたどり著きます。參拝を済ませたら、階段を半ばまで下ってみましょう。富士山のミニチュア版「品川富士」の入り口があります。標(biāo)高十?dāng)?shù)メートル、登頂までわずか2~3分。本物の富士山に登ったのと同じ御利益があるそうなので、ぜひチャレンジを。
毎年6月7日に近い金曜から日曜、品川神社例大祭(北の天王祭)が開(kāi)かれます。力自慢の若い衆(zhòng)が品川拍子という獨(dú)特なテンポに合せて神輿を擔(dān)ぐ様子を一目見(jiàn)ようと、多くのギャラリーでにぎわいます。
- 品川神社:平成26年5月撮影

平成26年5月撮影
ヤング坂本龍馬滯在を記念した新銅像
坂本龍馬と品川の縁は、一般にはあまり知られていないかもしれません。龍馬は若かりし頃、現(xiàn)在の京急「立會(huì)川」駅近くにあった土佐藩の鮫洲抱屋敷(浜川砲臺(tái))の警護(hù)職に動(dòng)員されていました。浜川砲臺(tái)と鮫洲抱屋敷を結(jié)ぶ連絡(luò)路は、立會(huì)川商店街の道路として現(xiàn)在に殘り、若き日の坂本龍馬もこの道を毎日歩いていました。
時(shí)を経て、2004年には鮫洲抱屋敷跡から砲臺(tái)の礎(chǔ)石が発見(jiàn)され、これを高知市に寄贈(zèng)。この御禮として、高知市が坂本龍馬の像を贈(zèng)ったという経緯があります。
この像はプラスチック製でしたが、テレビドラマの人気を受け、地元有志らによって立派なブロンズ像に生まれ変わりました。いまでもこの銅像を一目見(jiàn)ようと、龍馬ファンがこの地を訪れているようです。
激動(dòng)の幕末を物語(yǔ)る砲臺(tái)跡
北品川と砲臺(tái)に関する幕末エピソードは數(shù)多く殘されています。北品川の地に殘る「臺(tái)場(chǎng)」の地名は、砲臺(tái)を設(shè)置した要塞のこと。1853年のペリー來(lái)航で、幕府は1年後の再來(lái)航に備えた臺(tái)場(chǎng)建設(shè)を急ぎました。江戸灣の臺(tái)場(chǎng)は「品川臺(tái)場(chǎng)」と呼ばれ、品川の御殿山などから土を運(yùn)んで海上に人工島を作り、11基の砲臺(tái)設(shè)置を計(jì)畫したそうです。
このうち、実際に完成したのは8基。北品川の御殿山下臺(tái)場(chǎng)跡もその一つです。明治時(shí)代には品川燈臺(tái)が建てられ、現(xiàn)在は記念モニュメントが殘されています。
- 品川區(qū)立臺(tái)場(chǎng)小學(xué)校の校門そばにある御殿山下臺(tái)場(chǎng)跡
:平成26年5月撮影
北品川の運(yùn)河に浮かぶレトロな船著場(chǎng)
JR「品川」駅港南口から舊東海道方面に向かう途中、近代的なビルやマンションを抜けると、まるで昭和にタイムスリップしたかのような一角が現(xiàn)れます。運(yùn)河の行き止まりにある船著場(chǎng)です。
1945年代半ばくらいまで、品川沖と呼ばれていた海でノリの養(yǎng)殖が盛んに行われていました。しかし、品川埠頭建設(shè)工事が始まり、養(yǎng)殖場(chǎng)は埋め立てられてしまいます。これによって、船の持ち主たちは釣り船宿として再スタート。現(xiàn)在は屋形船も導(dǎo)入し、海の上から非日常的な東京灣を案內(nèi)しています。
- 運(yùn)河に並ぶ釣り船?屋形船:平成26年7月撮影





